
ファンドラップをサービスとして扱うことで、預り資産ビジネスの裾野が広がった
京都銀行 常務執行役員 田中基義 様
※所属部署・役職・対談内容については取材当時のものです。
「地域社会の繁栄に奉仕する~地域の成長を牽引しともに未来を創造する~」を経営理念に掲げる京都銀行様では、人生100年時代のライフステージに添ったコンサルティング・サービス拡充のため、2022年10月からウエルス・スクエアと提携したファンドラップ・サービス『京銀ファンドラップ』の取り扱いを開始しました。
ファンドラップの取り扱いを通じて、ビジネスモデルにどのような変化が起きたのか。また、地域に根ざす金融機関として今後どのような展望をお持ちでいるのか。京都銀行・常務の田中様にお話を聞かせていただきました。聞き手はウエルス・スクエアの星です。
お客さまと対話し、伴走できる存在を目指して
星:京銀ファンドラップの開始から1年が経ちました。ファンドラップの導入を決断された背景として、どのようなお考えがあったのでしょうか?

田中様:1941年創立の当行は「地域社会の繁栄に奉仕する」を経営理念に掲げ、地域金融機関としての使命を果たすべく、時代とともに変化するお客さまのニーズにお応えし続け、持続的な成長をとげてきました。
そうした歴史の中で、2017年に京銀証券を設立し、2018年には信託業務を開始しました。銀行・証券・信託のサービスを一気通貫に行うことで、お客さまの多様な資産運用のニーズにワンストップでお応えする体制を築き上げています。
一方、お客さま一人ひとりにご満足いただけるサービスを提供するためには、お客さまとの継続的なコミュニケーションが何よりも重要と考えています。資産運用における良き相談相手として、お客さまと伴走していける存在に我々はなっていく必要があります。
そうした背景から、ファンドラップは私たちの目指している姿と合致していると感じました。お客さまの資産運用へのご意向のヒアリングを起点とすることで、お客さまへのコンサルティングの質を高めることができるだろうと考えたからです。
ファンドラップを通じて、お客さまとのコミュニケーションをもっと大切にしていく。お客さまのニーズに適した金融サービスをしっかりと提案していく。そうした流れを行内全体に広めていくべく、ファンドラップの導入を決断しました。
ファンドラップを起点に、提案の裾野が広がった
星:様々な金融機関さんと話をさせていただく中で、「ファンドラップを導入すると、販売手数料などの収入が減り、収益が落ちてしまうのではないか」という懸念をよくいただきます。ファンドラップの導入にあたり、そういった声はありましたでしょうか?

田中様:導入において、懸念の声もあったのは事実です。ただ、お客さまに寄り添った資産運用を実現するためのサービスとして、ファンドラップと向き合っていけば、当行にとって長期的には確実にプラスになるだろうと確信していました。
また、ファンドラップの導入にあたって、ファンドラップ単体で販売していくモデルにはしないと考えていました。
長期的な資産運用サービスをご希望されるお客さまには、まずはファンドラップのヒアリングを実施させていただき、資産状況やリスク許容度をお伺いさせていただきます。その結果、ファンドラップではなくて、別のサービスや商品のほうが適していると判断した場合は、そちらを提案していきます。
我々が実現したいのは、ファンドラップを通じて、お客さまのニーズに適した提案をしていくことです。ファンドラップのヒアリングを、お客さまへのサービスの一貫として継続的に実施していく。この意識を行内全体で共有しています。
星:京都銀行様では多彩な商品をお持ちですが、ファンドラップのヒアリングを起点とすることで、お客さまへの提案の幅が広がっているということでしょうか。
田中様:そうですね。人生100年時代と言われる中、資産運用の必要性を感じているお客さまは増えていると思います。
そこで、ファンドラップのヒアリングを実施すると、お客さま自身も気づかれなかったような資産運用のニーズが見えてきます。その発見によって、これまでは検討されてこなかったサービスや商品へ興味を持たれることもあります。
お客さまがご利用するサービスや商品の裾野をどう広げていくかが、ここ数年の当行の課題だったのですが、ファンドラップの導入により変わってきたように感じています。
ファンドラップを商品ではなく、サービスと認識する
星:また、ファンドラップの取り扱いに際して、ウエルス・スクエアと提携をいただいていますが、我々のサポート体制についてはどのように感じてますでしょうか?
田中様:まずは、導入のはじめの段階から、熱心にサポートいただいたことをとても感謝しています。支店長向けにも、個人営業の担当者向けにも、何度も研修を実施していただき、大変ありがたく感じています。
ファンドラップの場合は、金融商品を売買する際に発生する手数料収入を中心としたフロー型ビジネスではなく、資産管理から発生する報酬を定期的に得ていくストック型のビジネスです。この違いを各支店長が理解できなかったら、ビジネスとしてうまくいきません。海外事例などを含めながら、丁寧に説明いただけたのでとても助かりました。
また、私がファンドラップへの理解を行内に広めるうえで特に気を配っていたのが、ファンドラップを「商品」ではなく「サービス」として認識してもらうことです。ファンドラップを取り扱う上で大切にしたいのは、お客さまのニーズに適した商品やサービスを提案していくことであって、ファンドラップ単体を売り込むことではありません。
ヒアリングの結果、お客さまの状況やニーズに適しているのであれば、ファンドラップを提案していく。その我々が目指しているところをウエルス・スクエアの皆さんが汲み取ってくださって、重ね重ね伝えてくださっていたのは本当にありがたかったです。
そういう風に伝えていただけると、支店長も現場の行員に説明しやすいですし、現場でもブレずにお客さまへ案内できるようになります。行内全体のファンドラップへの理解を共有する点でも、ウエルス・スクエアのサポートは大きかったと感じます。
ビジネスモデルの変革を推進していく
星:最後に、ファンドラップの取り扱いを継続させた先に目指している将来像について、お聞かせいただけますでしょうか?
田中様:2023年10月、京都銀行グループは持株会社体制へ移行し、「京都フィナンシャルグループ」として新たな一歩を踏み出しました。そして、我々の中期経営計画(2023 年度~2025 年度)では、預かり資産残高1兆円を目標として掲げています。
フロー型の収益を求めないわけではありませんが、フロー型よりストック型のほうに軸足を持っていく。それが現在の京都銀行の預かり資産ビジネスに対する取り組みの考え方です。こうしたビジネスモデルの変革を進めていくなかで、ファンドラップは中核を担うサービスだと感じています。
そもそも、ファンドラップの取り扱いがなかったら、ストック型のビジネスへ頭を切り替えることが難しかったのではないかと思います。お客さまに資産運用サービスを長期的にご利用いただき、残高を増やしていくことが、最終的に銀行の収益にも繋がる。その考え方にシフトできた要因として、ファンドラップの存在は大きいと感じます。
人生100年時代と言われる中で、お客さまの資産運用に関するご意向をしっかり聞き取り、お客さまの最善の利益に繋がるものを提供していく。その流れの中で、銀行として預かり資産ビジネスを拡大していきたいと考えています。
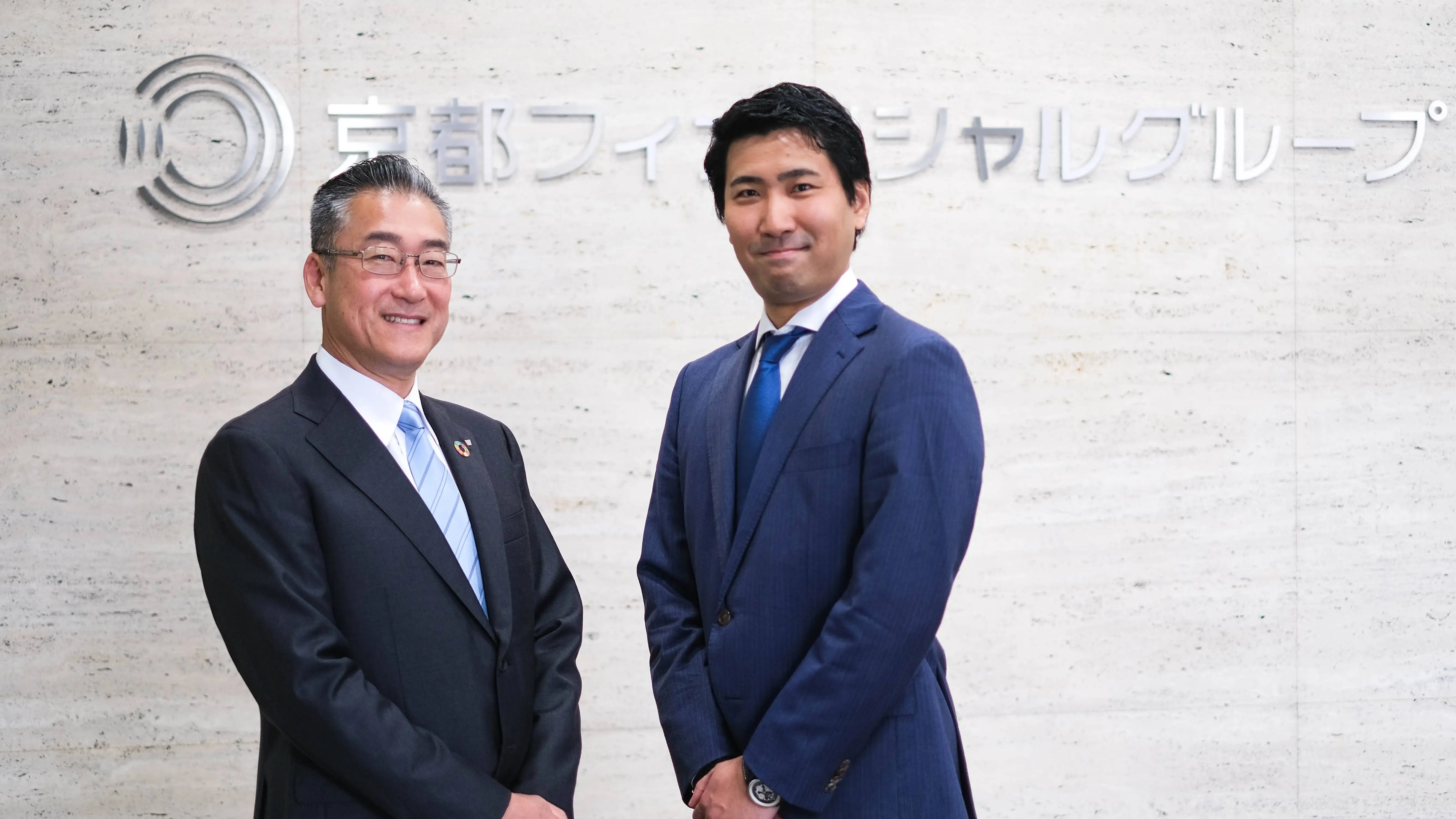

関連記事
-

地域のリーディングバンクとして、ファンドラップ導入の先に見据える未来像とは?
- 山陰合同銀行
- 常務執行役員
- 景山英俊 様
-

ファンドラップを継続的な取り組みにするには、思想的な部分の共有が欠かせない
- 山陰合同銀行
- アセットコンサルティング共同部長
- 友田耕生 様
-

ファンドラップによって、お客さまの夢について伺うことが増えた
- 山陰合同銀行
- 松江コンサルティングプラザ
- 福頼愛 様


